- 瞑想をやってみたけど思考が整理できない
- 実際やってみたけどあっているのか不安
- 瞑想の感覚が知りたい
こんな悩みを解決します!
瞑想を600日続けた私が丁寧に解説します。
私は仕事の都合で繁忙期があり、休日出勤が続いたり、長時間労働などで強いストレスを感じていました。日常でも常にストレスを抱えており本当に苦しかったのです。
そこで少しでも心を楽にするために始めたのがマインドフルネス瞑想。
すでに始めてから600日が過ぎ、状況は以前と180度変わっています!
長い前置きは飛ばして瞑想のポイント5選から解説してしまいます。その後に初心者が抱えやすい悩みに答える形式で瞑想のやり方についても解説するので是非ご覧にください!
もくじ
初心者が抑えるべきポイント5選
- まずは5~10分の短時間で行う
- 呼吸に集中する
- 楽な姿勢で行う
- 静かな環境を確保する
- 継続する
瞑想を始めてぶつかる2つの壁
- このやり方でいいのか分からない
- 思考が止まらない
焦らなくて大丈夫!止まらない思考に対処する2つのコツ
- 注意を向ける対象を作る
- 頭に浮かんでくる考えを認識してあげる
まとめ:まずは1つずつポイントを抑えることから!
初心者が抑えるべきポイント5選
瞑想を始めたばかりの時期はわからないことが多く不安も多いはずです。実際私も不安だらけでした。
そこで重要なのがある程度の流れと感覚をつかむことです。私が実際に始めたときに早く知りたかった情報ばかりですので、ぜひ今日からポイントを抑えた瞑想を実践してください!
瞑想時間は特に悩みやすいのではないでしょうか。結論としてはまず5~10分ほど瞑想を行ってください。
理由は2点あります。
1つ目は急に30~60分の瞑想を行うとほぼ必ず注意が散漫になり、負荷が高すぎるため瞑想をやった気になって終わることが多くなります。
2つ目は継続が難しいという点。ポイント5で詳しく説明いたしますが、瞑想の効果を得るには継続がすべてです。初心者が最初のやる気で長時間に挑戦し、1週間もたたずに燃え尽きてしまうのは容易に想像できます。
時間を延ばすのは5~10分が難なく行えるようになってからで全く問題ございません!
私も瞑想を始めて1週間で1時間の瞑想にチャレンジし、無事に挫折を経験しました…
これはいろいろなところで見飽きたよという方多いのではないでしょうか。詳しいポイントは後ほど「2つのコツ」の中で説明いたしますが、ここで抑えてほしいのは注意を集中する対象を決めること。
対象は呼吸やおなかの動き、音など何でもいいのですが、呼吸は一番身近でリズムが安定しているため注意を集中させる対象として最適です。
また最初の頃は座って何をすればいいかわからない方も多いかもしれません。
まずは呼吸のリズム(吸って吐くまでの一連のリズム)に集中すればいいんだなと思ってください!
これは当たり前のようで意外と適当になってしまうところです。瞑想は何となく座禅しないといけないのかなと思う人もいらっしゃるのではないでしょうか?
気にしなくて大丈夫です!
姿勢で気を付けるのは背筋を伸ばすことぐらいで、座る際は椅子、あぐら、座禅式など様々ですが、一番楽だと感じる姿勢で行ってください。
注意を集中させるためには静かな環境の確保が欠かせません。
私の実家で行っていた瞑想を例に挙げると、家族にいつ話しかけられてもおかしくないような昼間に行う瞑想と、家族が全員寝ていて確実に話しかけられない静かな自室でやる瞑想では注意を集中するレベルが格段に変わります。
私は一人暮らしのため他人が話しかけてくることはないですが、できるだけ騒音がなく集中しやすい朝の時間帯に行うことが多いです。
5つのポイントで一番重要なのがこの継続です。
瞑想は筋トレとよく似ています。トレーニングを行って、ある程度実感できるほどの効果を得るためには1か月~半年ほどは続ける必要があります。
それほど地道だからこそ、しっかりとポイントを押さえてしぶとく続けていくことが必要なのです。
しかしあなたにはこの5つのポイントがあるので大丈夫!続けやすいように皆さんはもう実践すればいいだけの状態にしてありますから、とにかくやってみてください!
瞑想を始めてぶつかる2つの壁
これは実際に私が600日続けた経験と瞑想経験者の体験をもとに、瞑想を始めたら必ずぶつかる壁を紹介させていただきます。
私は初期段階でかなり悩んでいたことですので、皆さんにはぜひサクッと乗り越えられるよう解説いたします。
このやり方でいいのか分からない
まず出てくるのがこのやり方であっているのか?という悩みです。初期段階は瞑想をしてみるものの効果を実感しづらく、自分の瞑想方法に疑問を持ってしまいがちです。
そのためやり方を調べていろいろ探っているうちによくわからなくなって面倒に感じてしまうのがオチです。
心配しなくて大丈夫です。実感できるのは少なくとも1か月はかかります。
まずはポイントを押さえて短時間で呼吸へすべての注意力を注ぐこと。そしてそのトレーニングの継続日数を増やすことです。効果は後からついきます!
この悩みはあなただけではありません。乗り越えられるので安心して続けていただいて大丈夫です!
思考が止まらない
これは私を含めて本当に多くの方が悩んでおられます。
呼吸に集中しようとすると、別の考えがひっきりなしに浮かんできてしまうのです。
そのため自分は全然瞑想がうまくできないと感じてしまうのです。
この問題も全く心配ありません。というよりも当たり前です!
その状態が普段の私たちなのです。おそらくひっきりなしに出てくる思考は自分の未来や過去に関するものばかりではなかったでしょうか?(過去のトラウマや明日の仕事、今日のご飯、友達との約束…)
大事なのは普段の生活で無意識のうちに、その思考が私たちに付きまとっていることを知ることなのです。
具体的な対処方法は次の項目で詳しく解説しますので、この厄介な思考の波にどのようにして対処すればいいかを学んでいきましょう。
焦らなくて大丈夫!止まらない思考に対処する2つのコツ
まずは注意を向ける対象を作りましょう。私のお勧めは呼吸のリズムに集中することです。
具体的にはゆっくり深呼吸をし、意識的に息を吸って、吐いていくのです。普段は無意識のうちに呼吸を行っていますので、初めは変な感じがしますがこれで大丈夫です。
空気が鼻を通って、肺、おなかが膨らんでいき、今度はおなか、肺が縮まるにつれて空気が身体から外へ出ていきます。この呼吸の流れだけに集中してください。
こうして呼吸に注意を向けていると気づかぬうちに、別のことを考えていることに気づきます。
先ほど出てきた思考の波ですね!これには二つ目のコツで対処します。
普段の私たちの中ではこの思考が無意識のうちにめぐっており、過去や未来に囚われてている状態にいます。
よく例えられるのが車の自動操縦状態です。車を運転する人は目的地に着くまで運転に集中していますので、ほとんどの人が途中の景色を覚えていません。とても綺麗な湖や花畑があったかもしれないのにそれを見ることができないのです。
これと同じことが人生でも起きているのです。
人生の運転者であるあなたが、過去や未来への不安や憧れに囚われて、得られるはずの今ある楽しみや達成感、感謝すべき人間関係などを見過ごしてしまっているのです。
瞑想はこの浮かんでくる過去や未来の思考に気づかせてくれます。
そしてこの人生の自動操縦状態から脱することができるのです。
この雑念の扱い方については別記事でさらに詳しく解説しますので是非そちらもご覧ください!
まとめ:まずは1か月続けてみよう!
これから始める方、挫折したけどもう一度一歩を踏み出そうという方は当記事の5ポイントを意識してまず1週間行ってみてください。
また習慣化が苦手だよという方は記録をするのがおすすめです。私は習慣トラッカーという記録アプリで瞑想した日を記録していました。続けている事実が目に見えて分かるとモチベーションも上がります。
今では習慣を記録しながら、瞑想を誘導してくれるアプリもありますので気になった方は使ってみると、始めやすいと思います。
【Awarefy】習慣化を助け、瞑想の補助をしてくれます!
また私が瞑想を学ぶきっかけとなった本もご紹介しますので、気になる方は是非ご覧にください。
あなたの瞑想体験をさらに1ランク上げてくれるはずです!



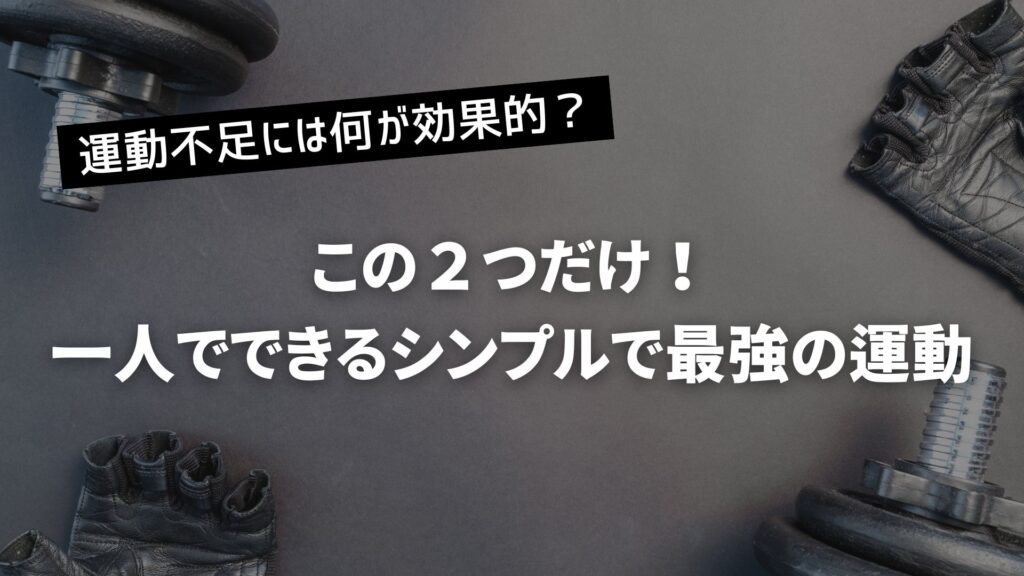
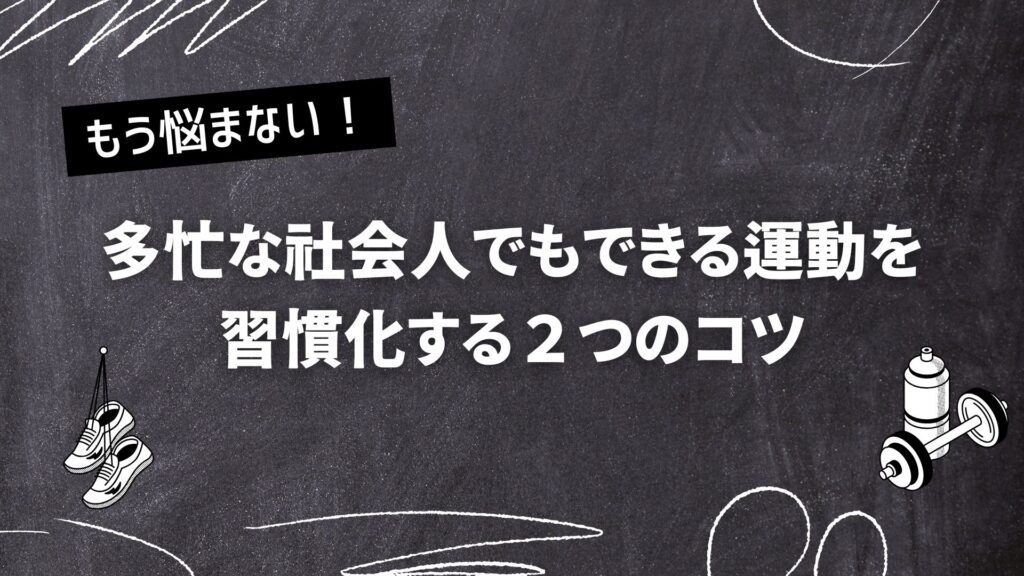

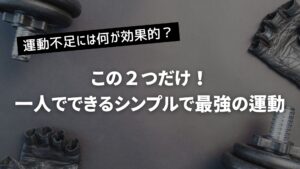




コメント